2010年01月19日
簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)
「調色」などの作業中、暗い場所では色の判別が付きにくいため、自作の照明器具を作ろうと計画しています。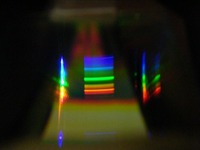
色の道 正しい「光」を求めて! (その1)
→ 簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)
撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)
高演色蛍光灯(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅳ)
電球型用インバーターで直管型蛍光灯を点灯(色の道Ⅴ)
高演色作業灯の作り方(電球型用インバーター使用 色の道Ⅵ)
高演色性の蛍光灯で、見え方はどう違うのか? (色の道Ⅶ)
最初は、持ち運びが簡単な小型バッテリーと白色LEDの組み合わせを予定していたのですが、どうも一般のLEDは「演色」(色の再現性)がイマイチのようです。
正確な色を判断するために重要な、最上の「光」を求めて、いろいろ調査してみました。

どんな光が良いのか、調べて行く中で、最初に目に付いたのが「分光器」。…簡単な工作で、各種、光の特性を自分の目で確認できるようです。
面白そうなので、さっそく、その分光器を作ってみました。
用意するのは、身近にある物ばかり。
適当な箱と、CDのディスク。他にアルミホイルとテープ類。
これだけで、30分もあれば、分光器を作ることができます。


CDは、光を当てると虹色に光ります。この性質を利用して、光を分解(分光)するパーツを作ります。
まず、CDのレーベル面に、カッターで切り込みを入れます。
 次に、プラ板用のカッターで、裏面からカット。
次に、プラ板用のカッターで、裏面からカット。
使いやすいよう、四角に整えておきます。
※レーベル部分の薄い膜が剥がれやすいので注意。


今回は手の平くらいの宅急便の箱を用意しました。
 光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。
光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。


スリットの部分は、アルミホイルを使います。
出来るだけ狭い間隔(0.5mm程度)で2本の切れ目を入れ、間の切りくずを取っておきます。
最初、斜めにカッターを当て、次に垂直に切ると簡単です。
カッターに引っかかって破ける場合があるので、事前に、セロテープで補強した方がいいでしょう。


まず、アルミホイルのスリット部分を箱に貼り付けます。
このままでは、ちょっと触っただけで変形してしまうので、上から半透明なシートを貼り重ねておきます。
このシートがあると光が拡散するので、箱の向きを光源に完全に合わせなくても、分光した虹を見ることができます。(A4クリアファイルを使用)


次に、CDから切り取った四角いパーツを取り付けます。
箱の覗き窓から見ながら、キレイな虹が見える位置を探して、その位置に納まるように箱の段ボールを折って、セロテープで貼り付けます。
元のCDが円盤状なので、できるだけ外周の部分で見るようにすると、平行に近い分光が得られます。
 余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。
余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。
これで、簡易分光器の完成。
箱を覗いてみると、光源によって全然違う虹が見えると思います。

▲太陽の虹

▲蛍光灯の虹
…このくらいの工作だと、夏休みの宿題みたいで、面白いです。
次は、この虹をカメラで撮影する器具を作ってみます。
→ 撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)
参考サイト
http://www.geocities.jp/hinaman_p/phy_cdmake.html
http://www.kagaku.info/spectrometer0605/index.htm
★今日、気になったサイト
ミサイルのように滑空する「弾丸ふくろう」の驚異的な写真にコメント殺到
中国、1日17億通以上もの携帯電話メールの検閲を開始
色の道 正しい「光」を求めて! (その1)
→ 簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)
撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)
高演色蛍光灯(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅳ)
電球型用インバーターで直管型蛍光灯を点灯(色の道Ⅴ)
高演色作業灯の作り方(電球型用インバーター使用 色の道Ⅵ)
高演色性の蛍光灯で、見え方はどう違うのか? (色の道Ⅶ)
最初は、持ち運びが簡単な小型バッテリーと白色LEDの組み合わせを予定していたのですが、どうも一般のLEDは「演色」(色の再現性)がイマイチのようです。
正確な色を判断するために重要な、最上の「光」を求めて、いろいろ調査してみました。
どんな光が良いのか、調べて行く中で、最初に目に付いたのが「分光器」。…簡単な工作で、各種、光の特性を自分の目で確認できるようです。
面白そうなので、さっそく、その分光器を作ってみました。
用意するのは、身近にある物ばかり。
適当な箱と、CDのディスク。他にアルミホイルとテープ類。
これだけで、30分もあれば、分光器を作ることができます。
■1、CDをカット


CDは、光を当てると虹色に光ります。この性質を利用して、光を分解(分光)するパーツを作ります。
まず、CDのレーベル面に、カッターで切り込みを入れます。
使いやすいよう、四角に整えておきます。
※レーベル部分の薄い膜が剥がれやすいので注意。
■2、箱の加工


今回は手の平くらいの宅急便の箱を用意しました。
 光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。
光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。■3、スリット部の製作


スリットの部分は、アルミホイルを使います。
出来るだけ狭い間隔(0.5mm程度)で2本の切れ目を入れ、間の切りくずを取っておきます。
最初、斜めにカッターを当て、次に垂直に切ると簡単です。
カッターに引っかかって破ける場合があるので、事前に、セロテープで補強した方がいいでしょう。
■4、組み立て


まず、アルミホイルのスリット部分を箱に貼り付けます。
このままでは、ちょっと触っただけで変形してしまうので、上から半透明なシートを貼り重ねておきます。
このシートがあると光が拡散するので、箱の向きを光源に完全に合わせなくても、分光した虹を見ることができます。(A4クリアファイルを使用)


次に、CDから切り取った四角いパーツを取り付けます。
箱の覗き窓から見ながら、キレイな虹が見える位置を探して、その位置に納まるように箱の段ボールを折って、セロテープで貼り付けます。
元のCDが円盤状なので、できるだけ外周の部分で見るようにすると、平行に近い分光が得られます。
 余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。
余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。これで、簡易分光器の完成。
箱を覗いてみると、光源によって全然違う虹が見えると思います。

▲太陽の虹

▲蛍光灯の虹
…このくらいの工作だと、夏休みの宿題みたいで、面白いです。
次は、この虹をカメラで撮影する器具を作ってみます。
→ 撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)
参考サイト
http://www.geocities.jp/hinaman_p/phy_cdmake.html
http://www.kagaku.info/spectrometer0605/index.htm
★今日、気になったサイト
ミサイルのように滑空する「弾丸ふくろう」の驚異的な写真にコメント殺到
中国、1日17億通以上もの携帯電話メールの検閲を開始
この記事へのコメント
ウ~ン(∋_∈)マニアックだ
実際に見てみたいっす
ばいや~。

実際に見てみたいっす

ばいや~。
Posted by 超酒酔人 at 2010年01月21日 01:30
あっ、これでマニアックってのが、普通の感覚なんだ!
そっかー、なんだか、ショック。
でも、いいんです。僕はマニアックの道を歩きます。
そっかー、なんだか、ショック。
でも、いいんです。僕はマニアックの道を歩きます。
Posted by IGU at 2010年01月21日 22:24
at 2010年01月21日 22:24
 at 2010年01月21日 22:24
at 2010年01月21日 22:24
これ、とても、いいですね。
週末工作で作って、
手元にあるいろいろなLEDの特性を調べてみようと思いました。
週末工作で作って、
手元にあるいろいろなLEDの特性を調べてみようと思いました。
Posted by 徹夜明け at 2014年03月05日 05:41
この次のエントリーで書いてますが、カメラをうまく固定すると、写真で比較できて便利です。
最近は高演色LEDが安くなってきたので、僕も近々に実験してみようと考えています。
最近は高演色LEDが安くなってきたので、僕も近々に実験してみようと考えています。
Posted by IGU at 2014年03月07日 18:59
at 2014年03月07日 18:59
 at 2014年03月07日 18:59
at 2014年03月07日 18:59※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。





















